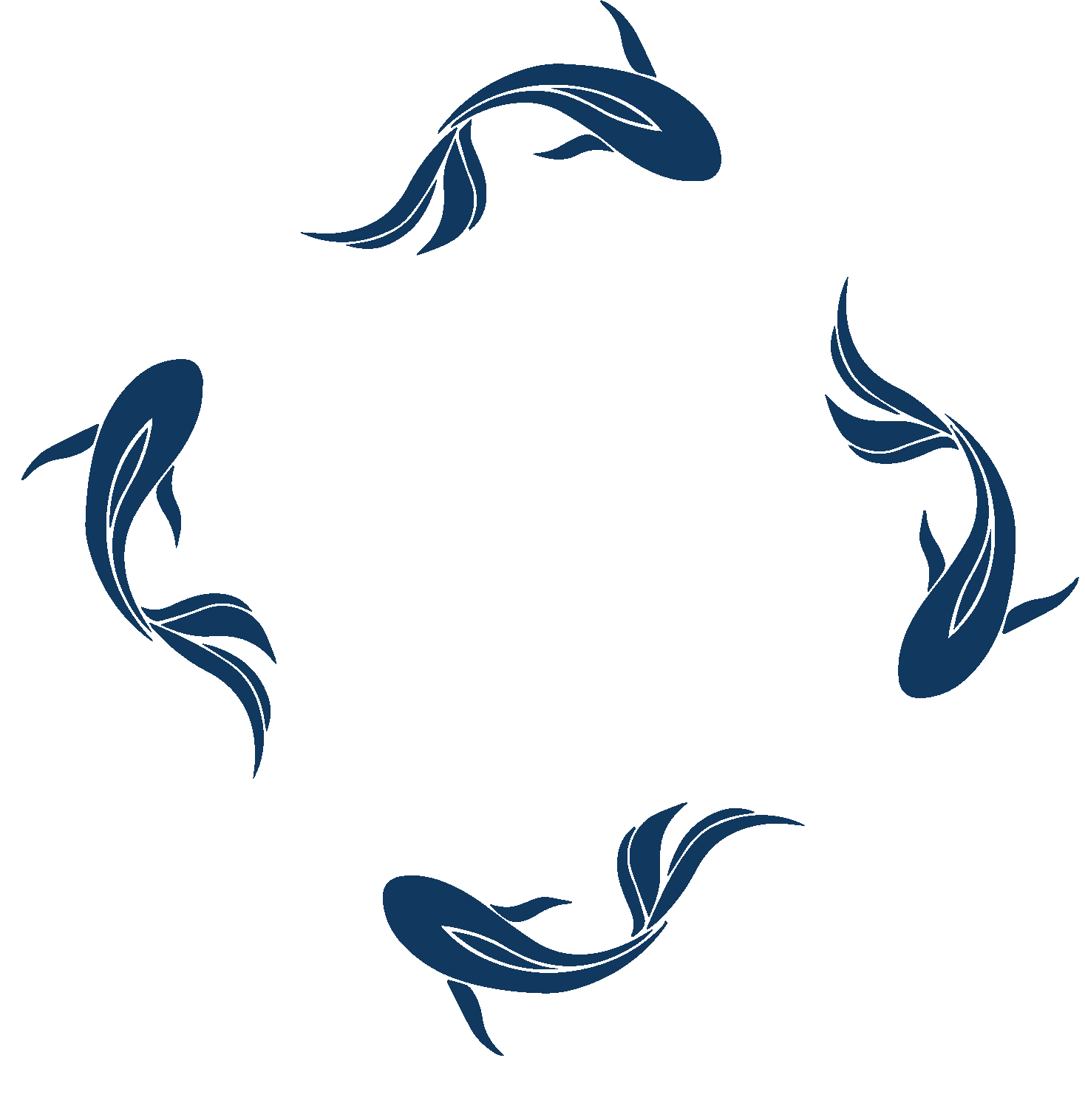友人に誘われ、ふと立ち寄ったパリ・マレ地区のギャラリー、タダエス・ロパック。足を踏み入れた瞬間、波紋のように広がる淡い色彩とアースカラーのペイントが、真っ白なキャンバスのようなギャラリーに溶け込んでいた。同時に、スピーカーから流れる歌声が、まるで教会の響きのように空間全体を包み込む。その場で思わず、「あ、動いている」と声が漏れた。
作家の名は、オリバー・ビアー(Oliver Beer)。彼の作品“Resonance Project: The Cave” (2024)は、音を「可視化」する という試みをしている。彼はフランス・ドルドーニュ地方の先史時代の洞窟を楽器として使い、ルーファス・ウェインライトやウッドキッドを含む8人の歌手とともに、空間の共鳴を「演奏」した。洞窟はまるで「歌い返す」かのように響き、音と歴史が交錯する没入型の体験が生まれた。さらに彼は、その音の振動を 「共鳴ペインティング(Resonance Paintings)」 という形で表現した。音波が絵の具を揺らし、キャンバスに見えない音の力を描き出す。つまり、音の波動が「絵」として残るのだ。
この展示を見たとき、自分の記憶の奥にある感覚が呼び覚まされた。昨年、ニューヨークで音楽パフォーマンスに招かれたときのこと。フィリピンの森を演出した水の流れる音、葉が擦れ合う音に加えて、ピアノとバイオリンが響いていた。その音を聞いているうちに、目の前に広がる音の波動が「ベージュ」に見えた。それを友人に話すと、「それ、共感覚(シナスタジア)だよ」と言われた。
音に色を感じる現象を 「共感覚(シナスタジア)」(Synesthesia) と呼ぶ。ある感覚が別の感覚を引き起こす現象のことだ。特に、音を聞いたときに色が見える現象は 「色聴(Chromesthesia)」 と言われる。意識していなかったが、自分はずっと「音を色で感じていた」のかもしれない。

英語には“I like your vibes” というスラングがある。最近、日本語でも「バイブスがいい」という表現を耳にするようになった。一見、「心地よい雰囲気」や「良い人柄」を指す単語に思えるが、掘り下げてみると、「バイブス(vibes)」はまさに音の振動(vibration)から派生した概念なのではないかと考えさせられる。音には、心地よいものもあれば、不快に感じるものもある。しかし、音そのものに「快・不快」の感情はない。それを決めるのは、人間の感覚だ。これは、人と人とのバイブスにも言えることだろう。
自分と相性の良いバイブスを持つ人に出会うと、「気が合う」と感じる。それは、お互いの波動が共鳴し、調和する瞬間なのかもしれない。人間関係も音と同じように、共鳴することで心地よい関係が生まれる。「バイブスが合う」というのは、言い換えれば、自分の周波数と相手の周波数が響き合っているということ。お互いのエネルギーが混ざり合い、響き合うことで、心地よい空間が生まれる。
相性のいいバイブスは調和する。でも、時には違うバイブスとぶつかることもある。それすら、新しい音楽を生む可能性があるのだから、それもまた良いではないか。心地よい波動が、自分のオーラやクリエーションと混ざり合い、デザインやアイデアとして形になっていく。そして、そうしたバイブスが多くの人と交わると、まるで合奏のようになり、そこに心地よい時間が生まれるのではないか。
僕はバイブスに非常に敏感だ。作品のインスピレーション、空間、人との関係——直感的に「心地よい波動」を本能的に追っている。音が共鳴するように、人との関係性も共鳴する。それが、自分のクリエーションの根源になっているのかもしれない。
この展示を見て、改めて「音・色・波動」がすべてつながっていると感じた。無音の中で作業する時間も、一度頭を白紙にすることで、響き合う波動を厳選し、シンプルな和音を奏でるような感覚になる。そして、僕自身がこれからも、波動を感じながら、作品を生み出していくのだろう。
稲木ジョージ
ミラモア創設者&金継ぎ哲学者